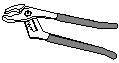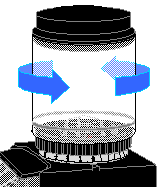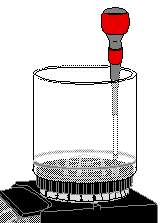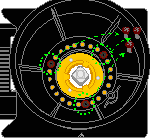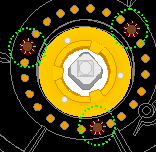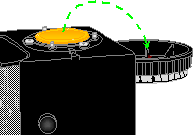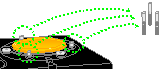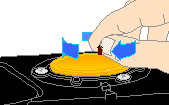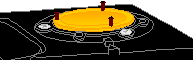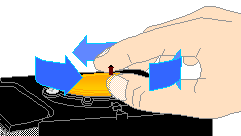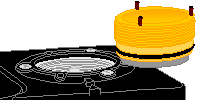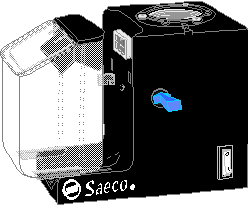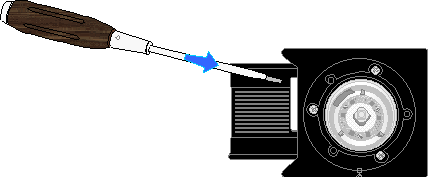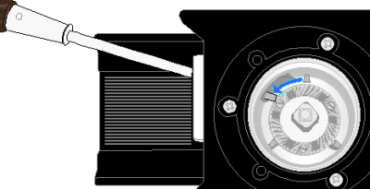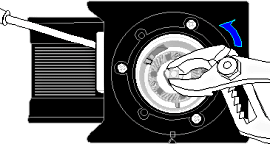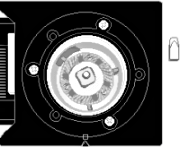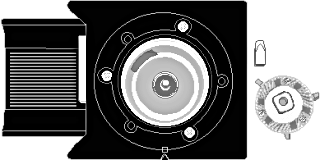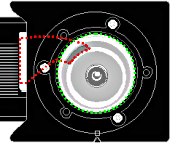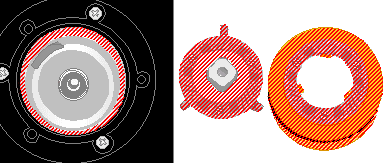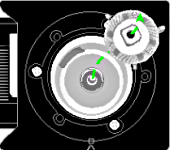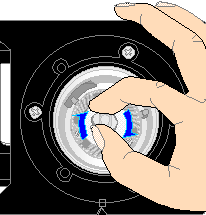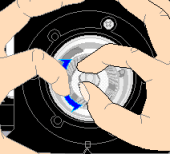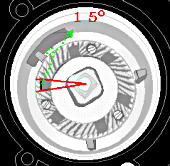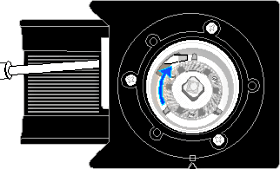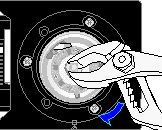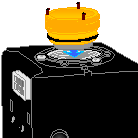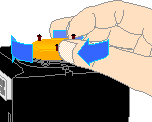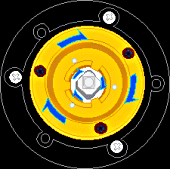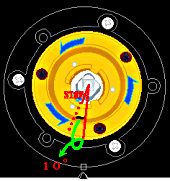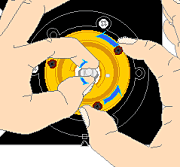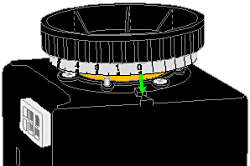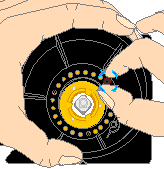|
|
 |
サエコ2002 |
 |
|
|
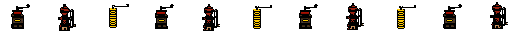 |
|
日本に於いて 良質のエスプレッソ=イタリアの味 が定着しつつある昨今ではありま |
|
すが、一つのファッションとしてエスプレッソを飲まれている方も多いのではないでしょう |
|
か。 |
|
最近では家庭用のエスプレッソメーカーも至る所で販売されています。 |
| しかし、実際に家庭でエスプレッソを楽しむとなると多くの問題が生じます。 |
|
特に、家庭で行うエスプレッソの抽出で、見落とされがちな部分は鮮度の良い豆を極 |
| 細挽きにすることが上げられます。 |
| エスプレッソが好きな人はShopで飲むエスプレッソをどうにか自宅で再現できないか? |
|
という願望から、小型のエスプレッソマシーンがあればきっと再現できるんじゃないか。 |
| と、安易に考えがちですが、しかし、そこには大きな落とし穴があります。 |
|
実際に購入して使用しているうちにShopで飲むエスプレッソと違うことに気付くでしょ |
|
| う。 |
|
この違いの大きな要因の1つに“市販のパウダーを使っている”もしくは“普通のミルを |
| 使って挽いている”ことが上げられます。 |
|
市販のパウダー(カートリッジポッドも同様)ではすでに酸化していますから、抽出した |
| コーヒーもすでに酸化臭/味があります。 |
| 豆(ホール)を買ってきて通常のミルで挽いてしまうと、“粒度が粗すぎる→お湯の通る |
| スピードが速すぎて成分が出てこない→粘性が低く、苦味だけがきつくシャバシャバのコ |
| ーヒーになってしまう” と言う図式が出来上がってしまいます。 |
|
普通のミルを使って最も細挽きにした粉では、エスプレッソ特有の粘性が高いコーヒー |
| にすことが出来ません。 |
|
エスプレッソの個性を活かすには、エスプレッソに合った新鮮な豆を抽出する直前に |
| 挽かなければなりません。 |
| 本場のイタリアではエスプレッソ1杯に対して1杯分の豆を挽くと言う概念(全自動マシー |
| ンは1杯分づつ挽く)が希薄です。 |
| (必ずしも イタリアのエスプレッソ味=凝縮したコーヒーの良質な味ではありません。) |
| 抽出理論と豆の相性が合致していない部分もあります。 |
| 当然、イタリアのエスプレッソミルは1杯分を挽ける構造にはなっていません。 |
| 日本製のミルでは極細にまで挽ける家庭用のミルはありません。 |
| そこでイタリア製の家庭用エスプレッソミルを改造して使うことになります。 |
| 問題点を細分化すると |
|
|
Page top |
|
1, |
ホッパーは豆をストックすることを前提として作られています。 |
| |
沢山豆を入れて挽くのであれば問題ないのですが、1杯づつ挽こうとするとスムーズ |
| |
にブレード内に入って行きません。 |
|
2, |
ブレードから出た豆が、ホッパーまでたどり着くまでのチューブ部分に粉が残ります。 |
| |
イタリアで売られている豆は粒が小さく現状のままでも良いのですが、日本で売 |
| |
られている(特に専門店)豆は粒が大きく、そのままではブレードの中に入って行きま |
| |
せん。 |
| |
改造する部分は、1杯づつ挽ける事とミルの入り口を広げる2点になります。 |
| |
エスプレッソミルは輸送コスト・為替差益の増減に対応する価格設定やブレードの |
| |
材質・精度・軸の精度・耐久性・販売量などの面で高価にならざる負えないのが現状 |
| |
です。 |
| |
ここで紹介するサエコ社2002でも3万円弱になます。 |
| |
小型のマシーンより高額で、決して安い買い物とは言えませんが、良質のエスプレッ |
| |
ソを家庭で楽しむに当たっては必携のアイティムです。 |
|
| |
|
エスプレッソマシーン購入時には、専用ミルも同時購入する事を念頭に入れてお |
| いて下さい。 |
| 因みに、当Shopではパボニー社のジョリーを改造して使用しています。 |
| (定価7万円)ブレードの口径が大きく2002より短時間で挽くことが出来・音も静かです。 |
|
| |
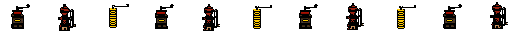
|
| |
OHに必要なモノ |
| |
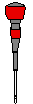 |
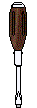 |
 |
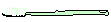 |
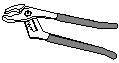 |
| +ドライバー |
−ドライバー |
消毒用アルコール |
ブラシ |
プライヤー |
|
| |
ウエス |
| |
分 解 |
| |
|
|
|
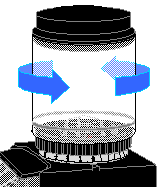 |
 |
ホッパー(メッシュ調節ダイヤル)を左に回 |
| |
し、止まるまでの最粗挽きにする |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
Page top |
|
|
|
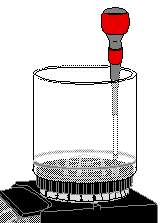 |
 |
ホッパー取り付けのねじを外し、ホッパー |
|
|
を外す |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
メッシュ調節ダイヤル取り付けのネジとスプリングワッシャー3つを外し、ダイヤ |
|
ルを外す |
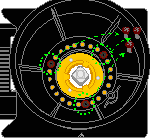 |
|
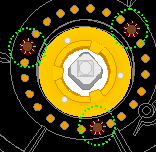 |
|
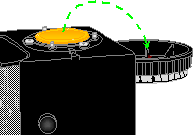 |
|
ネジをはずす |
|
ワッシャーが残るので、なくさないようにはずしておく |
|
ダイヤルを外す |
|
|
| |
 |
クリックピン3つを外す |
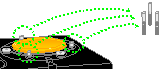 |
|
| |
 |
アッパーブレードアッセンブリーに、メッシュ調節ダイヤルを固定していた |
| |
3つのネジを(ネジ山部2mm程度)ねじ込む |
|
| |
|
|
|
Page top |
 |
ネジを持ち、左に回してアッパーブレードアッセンブリーを外す |
| |
|
|
| |
|
|
|
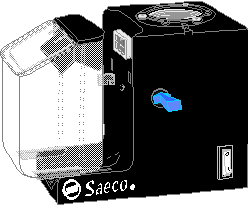 |
|
|
|
 |
リリースボタンを押してコンテナを外す |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
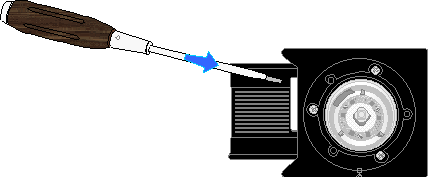 |
 |
粉の出口から− |
| |
ドライバーを差 |
| |
込む |
| |
(マイナス面が縦 |
| |
向き) |
|
| |
| |
|
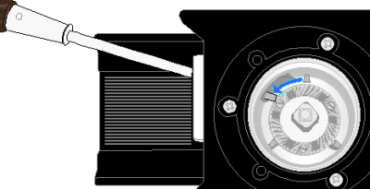 |
 |
アンダーブレードアッセン |
| |
ブリー
を左方向に回して |
| |
ウイングを固定する |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
Page top |
| |
|
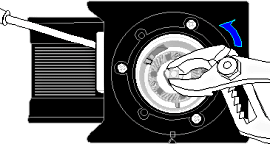 |
 |
センターシャフトキャップをプライヤーで |
| |
挟み左に回してキャップを緩める |
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| |
|
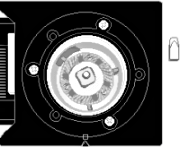 |
 |
更にキャップを手で回し外す |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| |
|
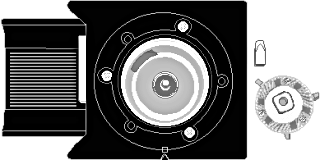 |
 |
アンダーブレードアッセンブリーを |
| |
センターシャフトから抜く |
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
分解完了 |
| |
清 掃 |
| |
 |
本体の内側の汚れ(粉)を掃除機で吸う(点線内に粉が付着しています。) |
| |
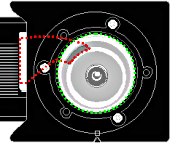
|
|
|
Page top |
|
| |
組 立 |
|
|
| |
|
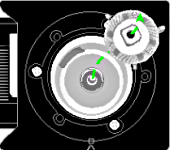
|
 |
センターシャフトにアンダーブレードアッセンブリ |
| |
ーを挿入する |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
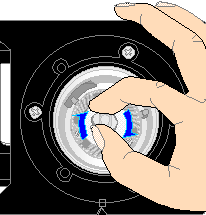
|
 |
センターシャフトにキャップを付け、手で止まるま |
|
|
で締める |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
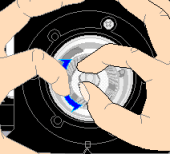
|
 |
キャップを少しゆるめアンダーブレードアッセンブリ |
| |
ーとの角度が手で締めたときに右図の様に、右手 |
| |
でキャップを持ちながら、左手でアンダーブレード |
| |
アッセンブリーを回して行く(締め付けて行くと約15 |
| |
度、角度がずれる。) |
|
|
Page top |
| |
|
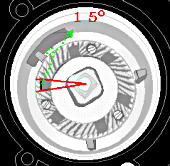
|
 |
もう一度センターシャフトにキャップを付け止 |
| |
まるまでしめる(手で) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
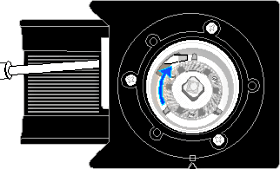 |
| |
|
 |
粉の出口から−ドライバーを差込、ア |
| |
ンダーブレードアッセンブリーを回し |
| |
て、ウイングのトコロを固定する |
| |
(マイナス面が横向き) |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
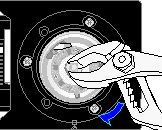
|
 |
センターシャフトキャップをプライヤーで挟み右に |
|
|
回して締めこむ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
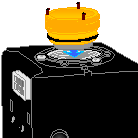 |
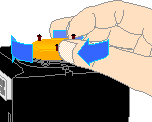 |
 |
アッパーブレードアッセンブリーを本 |
|
|
体に乗せ右にゆっくり回して行く |
|
|
締め込む際は無理せずゆっくり行 |
|
|
う! |
|
|
Page top |
|
|
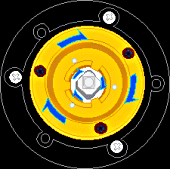 |
 |
アンダーブレードアッセンブリーも一緒に回り出した |
| |
時点で止める |
| |
(共回りしだした時が両ブレードの接触点です。) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
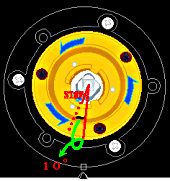
|
 |
アッパーブレードアッセンブリーを左回りに戻してゆ |
| |
き、アンダーブレードアッセンブリーが回らなくなっ |
| |
てから更に10度戻す |
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
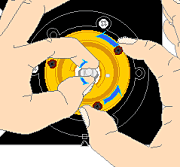
|
 |
手でキャップを掴み、アンダーブレードアッセンブリ |
| |
ーを動かしてみて(左右両方共に1回転以上回す)接 |
| |
触音が無くなるところまで、更に、アッパーブレード |
| |
アッセンブリーを戻す |
| |
|
|
|
|
 |
アッパーブレードアッセンブリーに取り付けたネジ3つを外す |
 |
クリックピン3つ(スプリングの方から)をクリックピンホールに入れる |
|
|
|
 |
メッシュ調節ダイヤルの目盛り「0」と本体 |
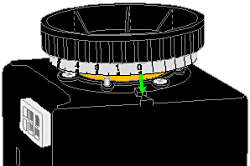 |
| |
のマーカーが一致するように乗せる |
| |
もしこの時にアッパーブレードホルダーのネ |
| |
ジ穴とダイヤルの穴とが一致しないときには、 |
| |
ダイヤルを左(細かい側)に穴1つ分を回して |
| |
調整します。 |
|
|
Page top |
| |
|
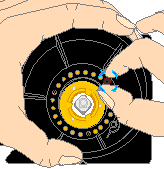
|
 |
メッシュ調節ダイヤルを左手で下に押さえ付け |
| |
3つのネジを取り付ける |
| |
|
| |
|
|
|
|
 |
コンテナを取り付ける |
 |
ホッパーを乗せネジで止める |
| |
(メッシュ調節ダイヤルのネジ穴とホッパーの穴とが一致するように乗せる。) |
|
| |
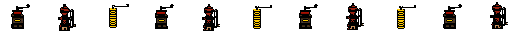 |
|

|
Go Back
|
 |