|

|
ドリップシステム |
 |
|
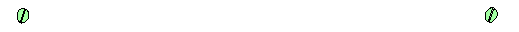
|
|
ヨーロッパのコーヒーの抽出方法で主流だったネルドリップを、1908年にドイツのメリ |
|
タ夫人が、誰でも簡単(美味しく)・もっと手軽に淹れられるペーパードリップのシステムを |
|
発明し、その後、徹底した研究・改良のもと現在ある形になっています。 |
|
ごく当たり前の抽出方法として広く世界の人々に愛用される様になりました。しかし、今 |
|
日の日本人の嗜好とずれが出てきている様に思われます。 |
| 当初の誰でも簡単(美味しく)には、メーカーの付ける条件の中で、一定の味になる。 |
| 言い換えれば、条件を外すと予定外の味が抽出される。 |
| 又、設定された味以外の味を求めるには、その条件を作ることが難しくなります。 |
| ここで注目したい物が、ペーパードリップの基になったネルドリップのシステムです。 |
|
ネルドリップでは注湯量を増やす程、お湯がコーヒーの層を通り抜けて下に落ちるスピ |
|
ードが速くなります。 |
|
これは上層部のお湯が下層部のお湯を押し下げようとする力(圧力)が増えて行くからで |
|
す。 |
|
|
注ぐ量と濾す能力(量) |
| フィルター内のお湯を最下層部とそれ以外の部分と分けて、 |
|
最下層部に掛かる圧力を比べると |
|
|
|
|
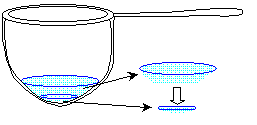
|
|
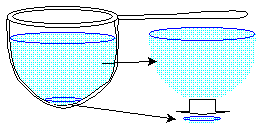 |
| 注ぐ量が少ないと最下部に掛かる圧力が弱く |
|
注ぐ量を増やすと最下部に掛かる圧力 |
| 濾す能力は低い |
|
が強くなり能力が高くなる |
|
| フィルター内にお湯を沢山入れると、下層部に掛かる圧力が増す事が解ります。 |
| 圧力が増すとフィルターを通り抜けるお湯の量が増え、通過スピードが速くなります。 |
|
スピードを変化させることが容易に出来る。このことが、熟練を要する最大のデメリット |
|
になり、逆に熟練すると円熟した深みのあるコーヒーを淹れるのに最も適した抽出である |
|
ともいえます。 |
|
初心者によくある速すぎた注湯スピードで淹れるコーヒーには、コクが無く、水っぽい味に |
|
なります。 |
|
又、ネルフィルターは何回も使用するため衛生面や簡易性(保存などの取り扱い。)にも |
|
問題がありました。 |
|
一方のペーパードリップで淹れるコーヒーは、ペーパーフィルターをドリッパーで支える |
|
ことによってお湯のスピードを強制的に抑えて、"速すぎたスピードで淹れるコーヒー"と言 |
|
う失敗を無くしました。そのかわりにスピードを変化させる事が出来なくなりました。 |
|
ネルドリップで作り出せる円熟した味のコーヒーはスピードを変化させることによって創り |
|
出せました。 |
|
|
注湯スピードを抑えるメカニズム |
|
ペーパードリップは、粉とフィルターの抵抗と、ドリッパーの内壁が一定量以上のお湯 |
|
が通過しないように、抑える働きがあります。 |
|
| |
|
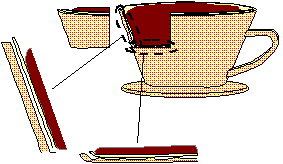
|
|
|
リブの高さ |
| ペーパーとドリッパー壁との隙間が狭 |
| いほど、お湯がフィルターの通過を抑 |
| 制する力が働き、濾過スピードが抑え |
| られる。 |
|
| リブの頂点(線)で、ペーパーフィルターを支え、フィルターから滲み出たコーヒー液は、
リ |
|
ブとリブの間のドリッパー内壁に沿って下方向に流れます。 |
|
|
ホースと板を使っての実験 |
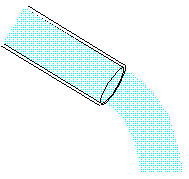 |
|
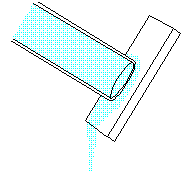 |
| ホースから出た水は、そのまま何の |
| 阻害もなく落下する。 |
| |
| |
| |
| |
|
|
| ホースの出口直前に板を置くと、1度出た |
| 水が行き場を失いホースに戻ろうとする力 |
| が生じる。 |
| 結果、流量が落ちます。 |
| この力はホースと板の間隔が狭くなると |
| より大きく働きます。 |
|
|
|
ペーパードリップはお湯の流れるスピードを強制的に制御しています。 |
|
好みの味になるようにスピードを調節する事は非常に難しくなります。又、ペーパーフィル |
|
ターが濡れることにより、ドリッパーの内壁に張り付き、隙間が無くなる事があります。 |
|
これはメーカーの想定し、設定しているスピードより注湯スピードが落ち、雑味の出る原因 |
|
となります。 |
|
しかし、衛生的であり、簡易性に優れているため、現在レギュラーコーヒーの抽出方法で |
|
主流になっています。 |
|
|
スピードマスター |
| ネルフィルターのように注湯量に比例したスピードを現実にします。 |
| 確実にドリッパー内壁とペーパーフィルターとのクリアランスを保ちます。 |
|
|
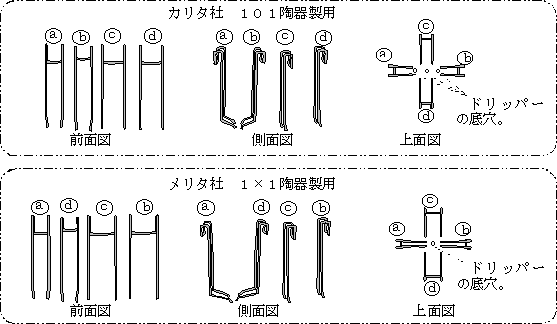
|
|
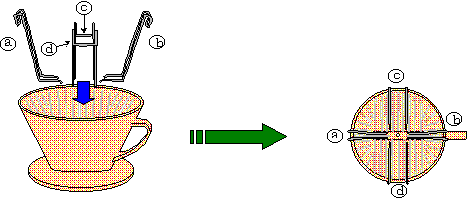
|
|
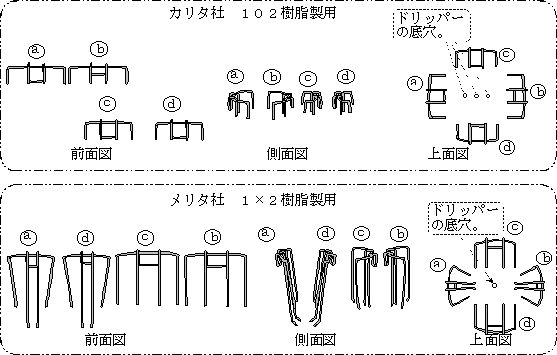
|
|
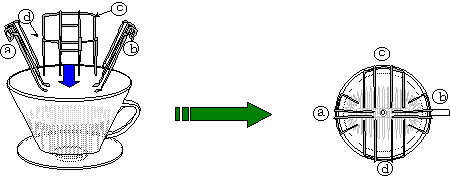
|
|
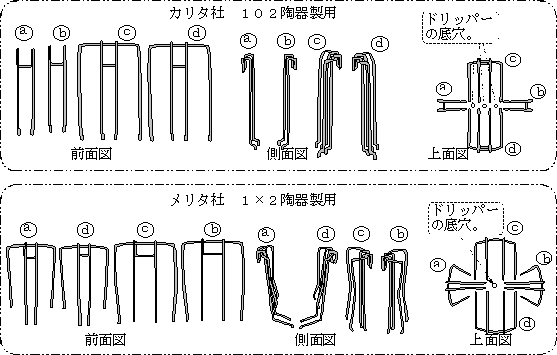
|
|
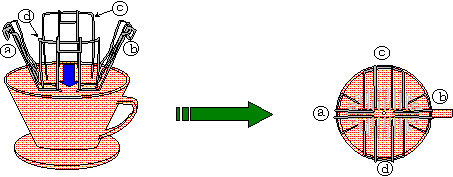
|
|
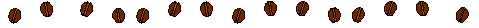
|
|
 |
|
 |