|
|
|
|
 |
Present |
 |
|
|
“抽出工程” |
|
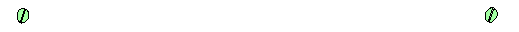 |
|
|
文字を書くことは簡単でしょうか。 |
|
|
|
文字の持つ役割によって、その答えは違います。 |
|
|
|
自身が、記憶できない情報を呼び起こす役割のメモ書き。 |
|
|
|
これは後で見返したとき、自分の脳へその情報をよみがえらせる事が出来れば、 |
|
|
|
どの様な形だって良い筈です。 |
|
|
|
では、その文字自体に人を惹き付けさせる魅力を、持たせること。 |
|
|
|
これは簡単に表せるでしょうか。 |
|
|
|
同じようにコーヒーも、シチュエーションによってやり方を変化させる事が、自然な成 |
|
|
|
り立ちではないでしょうか。 |
|
|
|
よって、この様な淹れ方をしなければならないと言う決めごとは存在しません。 |
|
|
|
しかし、“こんなテイストに仕上げたい”と思っているのに、採った方法が違っていれ |
|
|
|
ば、魔法でも使わない限り現実化は起こりません。 |
|
|
|
文字を書くにしても、絵を描くにしても“基本が大事”と言われます。 |
|
|
|
書道であれば“楷書体や行書体”の様に崩さない。元々の形状をしっかりイメージ |
|
|
|
出来てからデフォルメしなければ文字ではなくなって行きます。 |
|
|
|
絵画ならばデッサンですね。 |
|
|
|
描くのは見えている部分だけになりますが、現実では線がとぎれている訳ではあり |
|
|
|
せん。 |
|
|
|
見えていないが、続いている線の立体イメージ化が謀れずにデフォルメを行ってし |
|
|
|
うまと、唯の悪戯書きになってしまいます。 |
|
|
|
これに同感を覚える事は多いのですが、では、コーヒーの淹れ方の“基本”と聞か |
|
|
|
れると、どう説明すればよいのか迷ってしまいます。 |
|
|
|
いったいどこに“基本”が、あるのでしょうか? |
|
|
|
“楷書体や行書体”“デッサン”の基本は上達させれば、それであっても十分な味わ |
|
|
|
いを持ちます。 |
|
|
|
また、そこからのステップアップには、欠かすことの出来ない文字通りの基本的技 |
|
|
|
術が詰まっています。 |
|
|
|
だから基本に出来るのです。 |
|
|
|
しかし、コーヒーの場合は、今まで推奨されてきた方法を、“基本”と位置づけてしま |
|
|
|
うと、上達が望めなくなってしまうから、戸惑いを感じます。 |
|
|
|
“美味しくできない”それを素材の所為にすることは、間違いです。 |
|
|
|
“調節しない”“調節できない”ことは、唯、取っつきやすく間口を広げた方法でしか |
|
|
|
ありません。 |
|
|
|
HARMONYのライトボディーテイスト抽出(ドリップ)を、身につければフルボデテイス |
|
|
|
ト抽出へも充分応用を活かすことが出来ます。
|
|
|
|
勿論、逆の方向でも同様です。
|
|
|
|
ポットから流れ出る湯量がコントロール出来、尚かつ、層内でお湯がどの様に流れ |
|
|
|
て行くかが、認識できて行く(基本が身に付く)ほど、テイストはどんどん向上して行 |
|
|
|
きます。 |
|
|
|
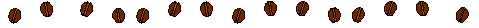 |
 |
|
 |