|
|
|
|
 |
Present |
 |
|
|
“素材の厳選と管理” |
|
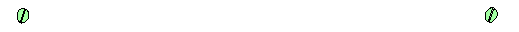 |
|
|
コーヒーの味は多次元でイメージすべきモノです次行程の4つうち、どの段階でも |
|
|
|
以前に戻って味を組み立て直すことは出来ません。 |
|
|
|
原料(生豆)“目利き”の如何によって、テーストは大きく違ってきます。 |
|
|
|
産地・農園や品種が全く同じであっても、収穫した時期の違いや保存状況によって |
|
|
|
もテーストに違いが出ます。 |
|
|
|
コーヒーの“目利き”は外観では予想できない部分が多く、見た目だけでの判断は |
|
|
|
中々、付けることが出来ません。 |
|
|
|
また、それ以降の行程を既成概念から外すと、他人の評価は全く当てにならないモ |
|
|
|
ノとなります。 |
|
|
|
確実に、それぞれの豆が持っている成分構成と性質を、素早く見つけ出すにはサ |
|
|
|
ンプルロースティングの技術と適切に判断出来る抽出技術・テイスティング技術が |
|
|
|
必要です。 |
|
|
|
産地などでテイスティングの資格を持った人だからと言って焙煎・抽出技術が優れ |
|
|
|
ている訳ではありません。 |
|
|
|
コーヒーを栽培している人も同じです。 |
|
|
|
焙煎機や抽出器具を設計製造している人たちも同様です。 |
|
|
|
このことを不思議と思われるかもしれませんね。 |
|
|
|
他の世界では当たり前に起こっていることです。 |
|
|
|
ゴルフクラブの設計者や製造に携わっている人達は、ゴルフが上手いと、言い切る |
|
|
|
ことが出来ないのと同じです。 |
|
|
|
技術レベルはトップアスリートの方が、絶対に上です。 |
|
|
|
では、トップアスリートが最高のクラブの設計・製造することが出来るでしょうか。 |
|
|
|
勿論出来ません。 |
|
|
|
共に違う能力を発揮するから、よい成績に現れるのです。 |
|
|
|
しかし、そんな現在の最高傑作のクラブであっても、時間が経過と共に平凡な一本 |
|
|
|
になっているかもしれません。 |
|
|
|
何が変わったのか? |
|
|
|
多くは新たな概念が発生したことによって、風化してしまったと感じたのです。 |
|
|
|
コーヒー界では、技術者と設計・製造者がテイストに向かって、突き進む事が見ら |
|
|
|
れません。 |
|
|
|
世界の競技大会の様な場所があってもです。 |
|
|
|
なぜなら、そのコンペティションでの採点にテイスト評価の割合が、低く抑えられて |
|
|
|
いるからです。 |
|
|
|
イベントにおいて魅力的に映ることは、見ても分からないテイストより、立ち回り・ト |
|
|
|
ークや表面に絵を上手に描く方なのです。 |
|
|
|
それによって、美味しく映った方が成功になるのです。 |
|
|
|
HARMONYでは、メーカーから出されたDataや一般的に言われている外観上のす |
|
|
|
べてをクリヤーしていたモノが、全く使い物にならないNG品(枯れ臭・カビ臭・薬品 |
|
|
|
臭)であった事を、頻繁に経験しています。 |
|
|
|
よって、現在テキスト化された情報は、信用していません。 |
|
|
|
HARMONYで行う目利きは、豆が持つ成分をデフォルメさせることなくそのままの成 |
|
|
|
分を評価します。 |
|
|
|
その為、サンプルは5〜6分と短時間で焙煎を行います。 |
|
|
|
フォーミュラサイフォン抽出術にて出来上がったコーヒーは温度帯を変えた3回と、 |
|
|
|
焙煎から日を置いて更に行った結果を判断します。 |
|
|
|
そのDataと共に外観上の総合判断で取り扱いを決定します。 |
|
|
|
外観上の判断は、欠点豆と色・サイズ・形の違う豆混入比率をみます。 |
|
|
|
これは、ポジティブハンドピッキングを行う上での作業工賃に、大きく関係しますが、 |
|
|
|
やはりテイストが第一です。 |
|
|
|
その行程を踏まえると、一般に出回る評価と全く違うモノとなります。 |
|
|
|
利益を最優先した方法では、人的な加工コストを掛けない事が鉄則です。 |
|
|
|
高品質と謳われた豆を、外観上きれいに仕上げて“AIDCAの法則”に沿って販売し |
|
|
|
た方が、販売ボリュームを遙かに巨大化させることが出来ます。 |
|
|
|
巨大になるほど利益率は上がり、儲かります。 |
|
|
|
しかし、本来の目的である高品質のテイストからは、どんどん離れて行きます。 |
|
|
|
企業として進めて行く方向は、生命まで削って行う事ではないかもしれませんが、 |
|
|
|
製品に納得できないモノを勧める。それが私共の仕事である。とは思えません。 |
|
|
|
その先に、もっとワクワクする様なテイストが待っている。 |
|
|
|
それをお伝えしなければならないと、考えています。 |
|
|
|
最近、ようやく原料の保存に気を遣うShopが増えてきました。 |
|
|
|
以前に信じられていた事は、“生豆は品質が変わりにくく長期保存が利く”というモノ |
|
|
|
でした。 |
|
|
|
その要因の一つは、日本に輸入された時点ですでに変化していた事。また、劣化ス |
|
|
|
ピードが速まった事も考えられます。 |
|
|
|
これは、ほとんど話題に乗りませんが、生産国・農園や収穫年度によって異なる。 |
|
|
|
このことから考えて行くと、コーヒー豆は生物と捉えなければ合点が行きません。 |
|
|
|
勿論、栽培・収穫・精選・保管方法のどこかに直接的な原因が、生じているはずで |
|
|
|
すが、大元を辿れば種族を世代交代によって引き継ぐ役目を担った種子(豆)に、 |
|
|
|
その仕組みを欠落させる様な仕業を人が行った。と見るのが妥当と考えます。 |
|
|
|
その仕業とは、いかに利益を上げるか。から始まりよいテイストを得るための目的
|
|
|
|
にカバーをさせています。 |
|
|
|
悪い味を取り去る行為が、生体を維持するシステムを外す事になった。と思われま |
|
|
|
す。 |
|
|
|
よって、以前に比べて格段に保存方法への配慮をしなくてはならなくなりました。 |
|
|
|
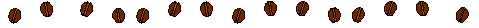 |
 |
|
 |