|
|
|
|
 |
Present |
 |
|
|
“良い酸味がある” |
|
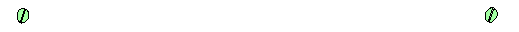 |
|
|
良い酸味があるコーヒーは、良質のアロマを強く感じる傾向にあります。 |
|
|
|
味覚成分の中で、条件反射が顕著に表れるのは“酸味”だけです。 |
|
|
|
| 生体に危険と感じさせるコーヒーの成分 |
| 苦み・渋み |
毒 |
| 酸味 |
腐敗したモノ |
|
|
|
|
これらコーヒーの主要味覚成分は、危険と判断させる成分を摂取しても安全と、学 |
|
|
|
習することで美味しく感じられる様に変化して行きます。 |
|
|
|
でも、これだけの理由なら、苦みや渋みも酸味と同様に、口に入れる前の条件反 |
|
|
|
射を起こして味を感じる筈です。 |
|
|
|
調べてみると、“酸味→酸”は歯を溶かすから”より早い段階で条件反射を起こさせ |
|
|
|
多量の唾液を分泌させ薄めてphを下げる。と言うモノでした。 |
|
|
|
それでも完全な説明とは考えてません。それを保護するだけであったら、唾液をよ |
|
|
|
り速く・沢山分泌させるだけで事が済み、見ただけで酸っぱく感じる必要はない筈で |
|
|
|
す。 |
|
|
|
おそらく、見ただけで多量な唾液を出してしまうと、体の方は何故出てくるの? |
|
|
|
いつまで出るの? |
|
|
|
これは、保護行為(条件反射)と情動(思考)が一致しなくなるからと、考えて良いと |
|
|
|
思われます。 |
|
|
|
“毒”について、少し、前のテレビ科学番組で取り上げていましたが、“ふぐ”の毒は |
|
|
|
致命的なので、学習(本能の蓄積)を行えない。と伝えていました。 |
|
|
|
確かに、ふぐを食べた個体のすべて死滅してしまえば、“これは危険”と認識して遺 |
|
|
|
伝子に残す事すら出来ないのは想像の通りと思います。 |
|
|
|
また、毒を調べて見ると“毒=苦み”ではないことも多く表示されます。 |
|
|
|
“テトロドトキシン”はふぐが持つ毒ですが、苦く感じ不味ければ無理して調理法を考 |
|
|
|
える必要はなかった筈です。 |
|
|
|
話が横道にそれましたが、現在、味覚や臭覚について研究発表されている事が |
|
|
|
すべて正しいとは思えないと、言うことを述べたいのです。 |
|
|
|
少なくても、機械が算出する数値や正しいと考えられている外部情報(既成概念)に |
|
|
|
依存するより、自身に元々備わっている能力を活かした方が、自身の正解を得ら |
|
|
|
れる。 |
|
|
|
このことが肝心だと思います。 |
|
|
|
だって、私たちは機械ではないのだから、あくまで主体は私たち人間の方なので |
|
|
|
す。 |
|
|
|
さて、“酸味”に戻します。 |
|
|
|
より迅速に反応したい成分と、考えられます。 |
|
|
|
その反応が、次の対処に反応出来るように、他の香りや味の成分もより敏感に感 |
|
|
|
じるようになるのではないかと、思います。 |
|
|
|
要は、聞き耳を立てた状態と同じように神経を集中させ、かすかな情報もPickUp し |
|
|
|
てしまうのではと、考えています。 |
|
|
|
これは、嫌悪するテイスト・好ましく感じるテイストと共に増幅して感じられ、個人差 |
|
|
|
によってその感覚バランスが異なるため、好ましいと判断した時には、更に良いテ |
|
|
|
イストに感じる。 |
|
|
|
逆に嫌悪と判断すれば、より不味いテイストと拡大解釈されているように思います。 |
|
|
|
コーヒーの酸味が嫌い。と、お思いの多くの方は、“酸味によって成分の劣化をよ |
|
|
|
り増幅させて感じた”や“テイストのバランスを崩した酸味”これらの情報(経験) |
|
|
|
によって、酸味があるコーヒーはすべて不味い。とインプリンティング(刷り込み)さ |
|
|
|
れた可能性が高いです。 |
|
|
|
特に、良質なコーヒーで嫌悪するのであれば、抽出を見直す必要があります。 |
|
|
|
現在、ほとんどの種類の豆に、強弱はともかく酸味成分が存在しています。 |
|
|
|
酸味は焙煎が進むことで焼失して行き、苦みは増して行きます。 |
|
|
|
また、一般的にはItalianRoastまで進めると酸味は消滅する。と言われます。 |
|
|
|
しかし、HARMONYで行っている焙煎の方法は、この殻(概念)を破りました。 |
|
|
|
苦み・ロースト香を高めたItalianRoastでも、甘みと一緒に微量の酸味をアフターテ |
|
|
|
イストに残します。 |
|
|
|
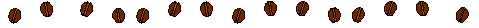 |
 |
|
 |